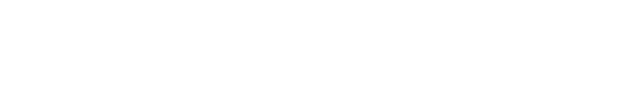医療・介護の生成AI/AIエージェント活用最前線レポート
AIとりわけ生成AIが登場してからのAIの進化のスピードには驚かされます。
ちょうど1年ほど前に医療現場で使用される生成AIについての記事を作成しましたが、記事中のツールはブラッシュアップされ、どんどん現場に入ってきています。
ついに医療現場でも生成AIが実用・実証開始 事例をみながら今後を考える
さらに「AIエージェント」という言葉も登場してききています。
「また新しい横文字か…」「うちの施設には関係ない話だ」と思われたかもしれません。
しかし、断言します。このテクノロジーは、もはや海外の一部の先進的な病院だけのものではなく、AIが「明日の現場を支える、身近で頼れるパートナー」になってきているということです。
本記事では、医療・介護の現場で今、実際に何が起きているのか、具体的な事例を豊富に交えながら、皆様の施設でも活用できるヒントを分かりやすく解説します。
ぜひ、同僚の皆様とも共有いただき、業務の革新について考えるきっかけとしてもご活用ください。
そもそも「生成AI」「AIエージェント」とは?
まず、言葉の整理から始めましょう。この二つの言葉を理解するだけで、日ごろのニュースなどの見え方がガラリと変わります。
生成AI (Generative AI)
これは、皆様も一度は耳にしたことがあるChatGPTに代表される技術です。大量のデータを学習し、それに基づいて新しい文章、要約、画像などを「生成」することを得意とします。
例えば、医療や介護の現場ですと、退院時サマリーの要約、ケアプランの文章作成、ご家族へのお知らせ文の作成などで利用が進んでいます。
AIエージェント (AI Agent)
こちらは、生成AIを脳の一部として搭載し、さらに自律的にタスクをこなす、より進化した存在です。与えられた目標に対し、自ら「①環境を認識し、②意思決定し、③行動を起こす」ことができます。
例えば、「ある患者さんの退院サマリーを作成して、これを関係各所に送付し、次回の予約まで調整しておく」といった、一連の業務を自律的に実行することです。
つまり、生成AIが「文章を書く」という単一のタスクを行うのに対し、AIエージェントは「文章を書き、それを使って次のアクションまで起こす」という、より複雑なワークフローを自動化できるのです。この「自律性」こそが、私たちの働き方を根底から変える可能性を秘めています。
現場での利用例
医療現場では、まず医師や看護師の大きな負担となっている事務作業から、AIの導入が驚異的なスピードで進んでいます。
電子カルテ自動作成
Pleap社が提供する「medimo」が一例です。
主な機能は、医師と患者の診察中の会話をAIがリアルタイムで聞き取り、わずか数秒でSOAP形式に準拠したカルテ原稿を自動で作成することです。
医療に特化して学習させた独自のAIを搭載しており、正確な医療用語を用いた質の高いカルテ作成を支援します。
電子カルテが対応している必要があるようですが、当院で使用しているモバカルは最近対応したようですのでとても楽しみです。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000124331.html
導入事例として、山口県の「波乗りクリニック」では、従来1時間近くかかっていた医師によるカルテ修正作業がほぼ不要となり、医師のカルテ業務を実質的にゼロに近づけることに成功したようです。
電子カルテデータからの医療文書自動生成
ALY社の「alyアシスタント」、Ubie社の「ユビーメディカルナビ」、NEC社の「MegaOak AIメディカルアシスト」などが一例です。
電子カルテに蓄積された診断名、処方、検査結果といった構造化データをAIが読み取り、退院時サマリーや診療情報提供書(紹介状)といった医療文書のドラフトを自動で生成します 。
東北大学病院とNECの共同開発では、この技術により文書作成時間を47%削減するという成果が報告されており、医師の事務作業負担を大幅に軽減しています 。
https://jpn.nec.com/medical_healthcare/aimedicalassist/index.html
対話型疾患説明生成AI
大阪国際がんセンターは、医薬基盤・健康・栄養研究所および日本IBMと共同で、2024年8月から乳がん患者様向けの「対話型疾患説明生成AI」の実運用を開始しました 。
このシステムは、AIアバターと生成AIチャットボットを組み合わせたものです。患者様は受診前の好きな時間に、スマートフォンなどから疾患説明動画を視聴したり、AIに自由に質問したりすることで、ご自身の病気や治療への理解を深めることができます 。
従来、約1時間を要していた疾患説明と同意取得の時間を30%削減することを目指しており、医師の負担軽減と、専門医不足による地域格差の是正が期待されています。患者様からは「不確かな情報が多い中、確かな情報が得られる」「医師には遠慮してしまう質問も事前にできて不安が和らいだ」といった肯定的な声が寄せられています 。
今後は消化管内科への展開や、問診・看護記録・サマリー作成を支援するAIシステムの導入も予定されています 。
https://oici.jp/center/news/3479/
ケアプラン(サービス提供票)自動作成
ウェルモ社の「ミルモプラン」、ベネッセ社の「マジ神」などが一例です。
アセスメント情報から利用者様に合ったニーズや目標を提案したり、ケアプラン作成のための気づきや提案を行うシステムで、ケアプラン作成の手間を省きます。短時間で質の高いケアプランが作成でき、空いた時間をヒアリング等に注力し、さらに経験の浅い職員でも質の高い視点で利用者を理解し、科学的根拠に基づいた個別性の高いケアを提供できるよう支援します。
https://dxmcnavi.com/solutions/milmo-plan/
業務運営の効率化
施設の運営面でも生成AIは活躍の場を広げていいます。職員の希望やスキル、利用者のニーズを考慮した最適な勤務シフトを自動作成するシステム や、パナソニックの「DRIVEBOSS」 のように、デイサービスなどの送迎計画とルートをAIが自動で最適化するサービスも登場しており、管理業務の負担を大幅に削減しています。
https://driveboss.automotive.panasonic.com/
AIキャラクター活用によるデジタルヒューマン
タレントの野々村真さんをモデルにしたAIアバターと対話する実証実験が介護施設で開始されました。
個々の高齢者の会話のテンポに合わせて対話を提供し、認知機能の改善を目指すという、ユニークな取り組みです。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000144306.html
まとめ
AIの進化は、私たちから仕事を奪うためにあるのではないと言われます。
AIは、私たちがこれまで忙殺されてきた記録、報告、調整といったノンコア業務を肩代わりしてくれることで、人間が本来やるべき、人間にしかできない仕事—患者様・利用者様の目を見て、手を握り、心に寄り添う温かいコミュニケーションや、深い経験に裏打ちされた専門的な判断—に、より多くの時間を注ぐことを可能にしてくれるます。
この記事が、未来の医療・介護のあり方を考えるきっかけとなれば幸いです。
まずは、「私たちの現場で、一番負担になっている業務は何か?」「その課題を解決するために、AIの力を借りられる部分はないか?」を考えるのが重要なことです。
当ホームページを見て下さる方の多くは、医療介護の関係者あるいは患者様、利用者様です。今回まとめた内容が少しでもお役に立ちましたら、ぜひ同僚や他施設の知人の方々にもご共有くださいませ。
業界全体でこの大きな変革の波を乗りこなし、より良い未来を共に創っていくための一助となれば、これに勝る喜びはありません。
医療法人ききょう会は東京都から埼玉県まで広く在宅医療(訪問診療)の提供を行っており、特に在宅ホスピスケア・緩和ケアに力を入れています。医療の質を向上させるためにDX(デジタルトランスフォーメーション)にも積極的に取り組んでいます。
・巣鴨ホームクリニック
豊島区、北区、文京区、板橋区
・東十条クリニック
豊島区、北区、文京区、板橋区、足立区
・花畑クリニック
足立区、葛飾区、埼玉県草加市、八潮市
・伊奈クリニック
埼玉県上尾市、桶川市、伊奈町、蓮田市、さいたま市見沼区・北区・岩槻区