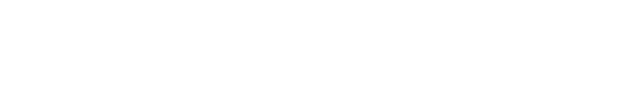病院でも自宅でもない中間の選択肢―新しいホスピス型ホームと在宅医療の連携
「自宅で看取る」を支える医療法人社団ききょう会
ききょう会は、長年にわたって在宅でのホスピスケアや緩和ケアに力を入れてきました。
終末期において病院の緩和ケア病棟を利用する選択肢はもちろんありますが、「やはり最期まで住み慣れた地域や自宅で過ごしたい」という想いを持つ方は少なくありません。
そうした患者さんに対応するため、ききょう会の各クリニックは24時間365日体制で定期往診や緊急往診に対応し、末期のがんや心不全、呼吸器疾患、神経難病などの重い病状でもできる限り在宅で過ごせるような仕組みを整えてきました。
ききょう会の訪問診療について
その中で、頻回な輸血や複数の管(点滴や胃ろう・中心静脈栄養・人工呼吸器など)の管理が必要な患者さんなど医療的な難しさがある方、低所得者などの社会的課題を抱えている方、あるいは独居で見守り体制が難しい方など、通常の在宅医療体制だけでは対応が難しいケースも存在します。
そうした「もう少し支援の厚みが欲しい」ケースに対し、この度、ききょう会が新たに連携を深めているのが、足立区に誕生した新しい形のホスピス型有料老人ホームです。
ホスピス型有料老人ホームとの連携がもたらす新しい選択肢
高い医療依存度に加えて複雑な社会事情
「毎週輸血が必要な患者さんを、病院と同じように施設で受け入れられませんか?」という相談が出るなど、ききょう会には高度な医療処置を必要とする在宅患者さんに関する問い合わせが絶えません。
病院の緩和ケア病棟と比較すると、自宅ではもちろん介護施設ではここまでの医療的対応は難しいケースが多いのが現状です。
また、低所得者や独居の方、家族はいるが疎遠な方など様々な事情で、医療面だけでなく社会的にもサポートが必要な患者さんもおり、このようなケースでは、退院先・転院先の調整が非常に困難になることがあります。
とくに終末期においては「病院から家に帰りたいけれど、高度な医療が必要だ」「施設職員や家族だけでは支えきれない」「いつ急変するか分からないのが怖い」ということで、帰りたいけど帰れないというジレンマを抱えがちです。
こうした中で、ホスピス型の有料老人ホームとききょう会が連携することで、在宅ホスピスケアに準じた柔軟なケアを行いつつ、医療依存度が高い患者さんでも施設で受け入れるという選択肢が生まれてきています。
“自宅の延長”としての暮らし
在宅ホスピスケアを支援してきたききょう会の視点から見ると、このようなホスピス型有料老人ホームは、「自宅と病院の間を橋渡しする場所」という位置づけになると思っています。
元々は自宅で過ごしたいと思っていた方が、独居や家族の介護力の問題で実現できない場合にも、自宅に近い感覚で暮らし続けられるよう、充実した各種医療処置や介護サービスを受けることが出来ます。
具体的には、次のようなことを行っています。
- 頻回の輸血が必要なケースでも、ききょう会の訪問診療チームや看護師が連携しながら、病院と同等レベルの輸血管理を実施できる体制を検討
- 胃ろうや中心静脈栄養(IVH)、人工呼吸器など、複数の管を必要とする方のケアに対応
- がん終末期など先が読みにくい場合にも、24時間見守りと医師のバックアップを整え、必要に応じて病院と連携
こういったサポートを、高齢者施設という環境の中で受けられることは大きなメリットです。もちろん医療費や居住費などの費用面では調整が必要ですが、関係各所の調整により低所得や生活保護の方でも可能な限り受け入れられるようにする仕組みづくりを進めています。
退院先から最期までをトータルに支援
従来であれば、「重い医療依存度の患者さんは病院へ」「在宅での終末期医療はそこまで医療負担が高くない患者さんが対象」という図式が一般的でした。ところが、近年は患者さん自身やご家族のニーズが多様化し、病院での治療を望まない一方で在宅に戻るには不安があるといったケースが増えています。
ホスピス型有料老人ホームでは、病院から退院してきた患者さんのケアを在宅ホスピスのように提供するため、自宅と同じように家族や友人の面会がしやすいというメリットがあります。
多職種・多機関の協力体制
病院・施設の緊密な連絡
在宅ホスピスケア・緩和ケアでは、多職種や多機関の連携が欠かせません。本ホスピス型有料老人ホームの場合も、ききょう会の医師・看護師・相談員が、病院や施設スタッフ、ケアマネジャー、ケースワーカーなどと連携しながら患者さんの状態を共有します。
そして、受け入れが難しいと諦める方向に持って行くのではなく「どうやって可能にするかを考える体制」を整えるようにしています。
輸血や点滴などをはじめ、高度な処置が必要なケースでも、まずは病院と方針をすり合わせ、「何をどのように施設内で継続できるか」を検討します。いつ、どのように、誰が、何をできるかをチームで話し合い、必要があれば地域の病院とも連携を継続しながら柔軟に対応していく仕組みを作っています。
社会的課題へのアプローチ
低所得や独居の方の場合は、医療費や生活費の問題だけでなく、誰が本人を支え、意思決定や看取りを見守るのかといった問題も生じます。
この点については、ききょう会が普段から連携しているケアマネジャーや地域包括支援センター、ケースワーカーなどと連絡を密にし、社会福祉制度の活用や公的支援を組み合わせることで解決策を模索しています。
患者さん一人ひとりの経済状況や家族状況等にあわせて診療回数を調整したり、訪問看護ステーションと役割分担して「どこまで削ってどこを手厚くするか」を調整しながら、患者さんが必要なケアを無理なく受けられるよう取り組んでいます。
ホスピスケアに準じた新しいモデル
これまで病院が担ってきた高度な医療ケアを有料老人ホームで柔軟に提供することはいわば、緩和ケア病棟の機能を有料老人ホーム内で実現する試みです。
必要があれば病院と連携して再入院も視野に入れつつ、最後まで施設で過ごすことも可能という選択肢が提供されるのは非常に意義の大きいことです。
「自宅→高齢者施設→病院」という従来のパターンだけではなく、「自宅→ホスピス型有料老人ホーム」や「病院退院→ホスピス型有料老人ホーム」で最期のときを過ごすという流れが当たり前になる日も遠くないかもしれません。
ききょう会がこうした新しいモデルに積極的に関わる背景には、地域医療の中で「最後まで安心できる場所」を増やしたいという想いがあります。
とりわけ足立区のように高齢者人口の多い地域では、「在宅に戻るのは不安だけれど、病院は制限が多くて快適とは言い難い」という声をよく聞きます。自宅でも病院でもない、第3の選択肢としてホスピス型有料老人ホームが普及すれば、地域の高齢者・患者さんはより多様な暮らし方を選べるようになるでしょう。
まとめ
今回ご紹介したホスピス型の有料老人ホームと医療法人社団ききょう会との連携は、医療依存度の高い患者さんや社会的に複雑な事情を持つ患者さんを在宅で最期まで受け入れる新しい選択肢になると考えています。
もちろん、まだまだ制度的な制約や費用負担の問題、スタッフの専門性確保といった課題は残っています。しかし、ききょう会のスタッフや施設の運営者は「まずは患者さんの希望を中心に据え、一緒にどうすれば可能になるかを考える」という前向きな姿勢で取り組んでおり、その積み重ねが新しい形を作っていく一歩になると考えています。
医療法人ききょう会は東京都から埼玉県まで広く在宅医療(訪問診療)の提供を行っており、特に在宅ホスピスケア・緩和ケアに力を入れています。
豊島区、北区、文京区、板橋区
豊島区、北区、文京区、板橋区、足立区
足立区、葛飾区、埼玉県草加市、八潮市
埼玉県上尾市、桶川市、伊奈町、蓮田市、さいたま市見沼区・北区・岩槻区