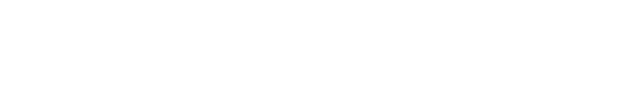映画『ハッピー☆エンド』が描く最期の時間の選択肢
人生の最期の時間の選択肢
現代の日本では、医療技術の発展とともに、病院で最期を迎えることが一般的になっています。
しかし近年は「できれば自宅で、家族とともに穏やかに過ごしたい」と望む方が増えているのも事実です。
その一方で「家で看取るのは現実的に難しいのでは」「家族に負担をかけてしまうのでは」といった心配や、「緩和ケア=治療の終わり」という誤ったイメージも根強く残っています。
そんな現状に一石を投じるのが、2025年4月18日に公開されたドキュメンタリー映画『ハッピー☆エンド』です。
この作品は、在宅緩和ケアを選んだ5組の家族と、それを支える萬田緑平医師(萬田診療所 群馬県)の日々を追いかけ、 「自宅で過ごす」という選択が、患者さんやご家族にどれほどの安らぎや喜びをもたらすのかを、リアルに描き出しています。
また、気になる方は、トークイベントもまだ行っているようですので要チェックです。
(以下、一部ネタバレ注意です)
たとえば、90歳の肺がんと食道がんを患った方は、退院時には歩くことも話すことも難しい状態でしたが、
自宅に戻ると驚くほど元気を取り戻し、庭を駆け回るまでに回復されたということです。
また、78歳の男性患者さんは複数のがんを抱えながらも、趣味のボートレースやお酒を楽しみ、 余命1か月と宣告されてから5年以上、笑顔で家族と日々を重ねているということです。
このようなケースでは「家が一番の薬だった」「家族と一緒に過ごせて本当によかった」という言葉が自然とご本人やご家族の口からこぼれ出しています。
この映画は、「人生の最終章」を自分自身で選択できる時代が来たこと、そしてその選択肢の一つとして「在宅緩和ケア」があることを、患者さんやご家族、医療・介護の現場で働く皆さまに伝えてくれています。
患者中心のケア
『ハッピー☆エンド』の大きな魅力のひとつは、「患者中心」というあり方です。
例えば、映画中では萬田医師は、白衣ではなく普段着で患者さん宅を訪れて患者さんにストレスを与えないような工夫をしています。また、患者さんと同じ目線で接したい、本人の思いを最優先したいと言っています。そこで、診察の合間には手品を披露したり、冗談を交わしたりと診察の場を明るい雰囲気で笑顔を作るための工夫しているというのは印象的です。
病院では、どうしても病気の「治療」「管理」が中心になりがちで、病気の治療が優先されることが多いのですが、 在宅緩和ケアでは「その人らしさ」を大切にしています。
よって、「好きな食べ物を味わう」「趣味に没頭する」「家族とゆっくり語り合う」という“その人らしい時間”を支えるのが、在宅緩和ケアの本質になってきます。
このようなケアにより、患者さんだけでなくご家族にとっても、「大切な人と日常の中でゆっくりとお別れの時間を持てた」「感謝の気持ちを伝え合えた」といった、かけがえのない思い出が残るのです。在宅緩和ケアは、患者さんだけでなく、ご家族の心の癒しにもつながるということです。
なお、ききょう会でも同様の考え方でケアを提供しています。
緩和ケアは最後の手段と言う誤解
緩和ケアは「もうできることがなくなった時の最終手段」というイメージを持つ方も少なくありません。
ですが、映画『ハッピー☆エンド』は、タイトルにもあるように「緩和ケア=その人らしい生き方を支える医療」でハッピーであるということを、 患者さんやご家族の姿を通して伝えています。
痛みや苦しみを和らげるだけでなく、「好きなことをして過ごす」「家族と一緒にいる」「自分の人生を自分で選ぶ」このような生き方を引き出し支えるのが、在宅緩和ケアの役割です。
また、在宅緩和ケアは「家族だけで背負うもの」ではありません。 医師、看護師、ケアマネジャー、訪問介護、地域包括支援センターなどの 多職種が連携して患者さんとご家族をサポートします。
「家で看取るのは不安」「家族だけで大丈夫だろうか」といった心配も、支援の輪がしっかりあることで安心に変わっていくということです。
映画でも、「在宅緩和ケアはチームで取り組むこと」「家族だけで抱え込まないこと」の大切さが繰り返し語られています。
患者さんだけでなくご家族にも「在宅緩和ケア」という選択肢の存在を伝える際のヒントとして、 この映画をぜひご覧いただきたいと思いました。
ききょう会が地域の多職種連携で作り上げる緩和ケア医療についてはこちらに記載しております。
「死」を明るく受け止める死生観
「死」や「人生の終わり方」について語ることは、重く、避けがちなテーマです。
しかし、映画『ハッピー☆エンド』は「どう生きるか」「どう最期を迎えるか」を温かく、前向きに考えるきっかけを与えてくれます。
作中では全身がんを抱えながら2018年に亡くなった女優・樹木希林さんの講演映像も織り交ぜられています。彼女は自宅に戻って最期の時間を過ごしましたが、その理由について、子供や孫にとって死を日常にしてあげたかった、そうすれば死が怖くなくなり、人を大事にするようになるからだと語っています。
最期の時間を悲しい別れではなく「感謝と笑顔に包まれた温かな時間」として過ごすという、生き方や看取り方もあるのだと、様々な事例を通じて教えてくれています。
実際に映画を観た方の口コミ等を見てみると「母は家のリビングで、子や孫に見守られながら安らかに旅立ちました。でも、それはとても温かい時間でした。この映画で伝えていることと同じでした。」、「夫に『自宅で最期を迎えたい』と言われるまで、在宅緩和ケアの存在を知りませんでした。今は私も、人生の最後はこうありたいと願っています」 「父と一緒にこの映画を観て、最後までお互い笑顔で過ごすことを決めました」 といった声がありました。
「死」を遠ざけるのではなく、「生きること」の延長線上にあるものとして受け入れる。そのためのヒントや勇気を、映画『ハッピー☆エンド』は私たちに与えてくれているということです。
地域で支える在宅緩和ケア・ホスピスケア
ききょう会は在宅緩和ケア・ホスピスケアを中心に在宅医療を提供しておりますが、在宅緩和ケアは「特別な人だけの選択」ではないと考えています。
自分や家族の最期をどんなふうに迎えたいかを考えるすべての方に開かれた選択肢だと考えています。
「自分らしく家で過ごしたい」「家族とゆっくり時間を持ちたい」「好きな人に会っておきたい」「好きなことをしながら最期を迎えたい」という思いを、どうか諦めないでほしいと考えています。
そのためにききょう会では、当院の医師、看護師、相談員をはじめ、連携する訪問看護ステーション、薬剤師、ケアマネジャー、訪問介護、病院の地域連携室などと工夫をして患者さんのケアを行っています。
そして、できるだけ選択肢を提示できるようにありたいと考えています。
そして、「病院医療を否定する」のではなく、「最良の選択ができるよう情報を届ける」ことも作中で語られており、同様にこれは私たちの役割でもあると考えています。
終末期医療の選択肢を増やす試みの一例
病院でも自宅でもない中間の選択肢―新しいホスピス型ホームと在宅医療の連携
医療法人ききょう会は東京都から埼玉県まで広く在宅医療(訪問診療)の提供を行っており、特に在宅ホスピスケア・緩和ケアに力を入れています。
・巣鴨ホームクリニック
豊島区、北区、文京区、板橋区
・東十条クリニック
豊島区、北区、文京区、板橋区、足立区
・花畑クリニック
足立区、葛飾区、埼玉県草加市、八潮市
・伊奈クリニック
埼玉県上尾市、桶川市、伊奈町、蓮田市、さいたま市見沼区・北区・岩槻区
(※本記事は映画公式サイト・各種報道・映画レビュー等をもとに作成しています。)