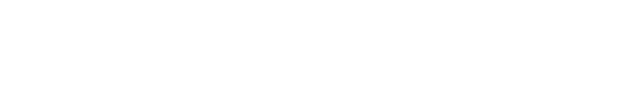ききょう会の訪問診療と在宅ホスピスケア
訪問診療について
お一人で通院するのが困難な方や介護を受けている方のご自宅に、医師が定期的に伺います。
基本的な診察に加え、簡単な検査(血液や心電図)、薬の処方や注射も可能です。
発熱や腹痛など急な症状が見られる場合にも24時間365日相談可能です。
必要に応じて緊急往診や病院の紹介を行います。
ケアマネジャー・訪問看護師・訪問薬剤師と連携し、住み慣れた地域で安心して過ごせるようサポートいたします。
対象の方
さまざまな理由で病院・医院への外来通院が困難な方が対象です
- 医療機関に通院していたが、通院することが難しくなってきた
- 近いうちに退院するように言われているが、今のまま自宅に帰るのでは退院後の生活や介護が不安
- 退院後も引き続き自宅での医療機器の使用が必要
- がんや難病、老衰などでも最期まで自宅で過ごしたい
- 在宅ホスピスケア、在宅緩和ケアを希望している
など、該当する方はお気軽にご相談ください。
対応可能処置・検査
自宅でも可能な処置等
- 点滴(病態に応じた点滴も可能です。例:肝性脳症時のアミノレバン®など)
- 在宅中心静脈栄養(ポンプ使用)
- 静脈注射
- 胃瘻経腸栄養、交換
- 腸瘻経腸栄養
- 経鼻経管栄養
- 在宅酸素療法(HOT)
- 在宅人工呼吸器、非侵襲性陽圧換気療法(NIPPV)
- 気管切開カニューレ交換、喀痰吸引
- 膀胱留置カテーテル
- 膀胱瘻や腎瘻の交換
- 人工肛門
- 褥瘡処置(陰圧閉鎖療法を含む)
- 医療用麻薬を用いた疼痛緩和ケア(持続皮下投与も可)
- 在宅輸血療法(照射濃厚赤血球、照射濃厚血小板)
- 腹水穿刺など
※上記については訪問看護ステーションとの連携が必要なものがあります。
※受け入れ件数に限度があるものもあり、確認の上、対応可能か回答いたします。
当クリニックで可能な検査
- 各種血液検査*、尿検査
- 各種培養検査*
- 血液ガス検査
- 超音波検査
- 心電図検査
- インフルエンザ迅速検査、帯状疱疹迅速検査
*は外注検査です。その他の検査が必要な場合は外部機関と連携して行います。
※当クリニックでは、在宅でも迅速検査(POCT:point of care testing)が行えるよう心がけています。
当クリニックで可能な予防接種
- インフルエンザワクチン
- 肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス®、プレベナー®)
訪問診療開始までの流れ
| 自宅療養中の場合 | 当クリニックへ直接ご相談ください。 介護保険利用中の場合は担当のケアマネジャーにご相談いただいても構いません。 |
|---|
| 入院中の場合 | 病院の医療相談室にご相談ください。 直接当クリニックへ電話をいただいても構いません。 |
|---|
| 施設入所中の場合 | 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム、 小規模多機能施設へは訪問診療が可能です。 希望される場合は、施設担当者とご相談の上、ご連絡ください。 |
|---|
お問い合わせから診療開始までの流れ
- 各クリニック医療相談窓口または
お問い合わせはこちら
お問い合わせ - 患者様の状態の確認
- 診療内容と費用のご説明
- 初回訪問日の決定
- 訪問診療開始
※通常月2回の訪問診療を行いますが、病状や要介護度に応じて、週1回の訪問や月1回の診察を行うことも可能です。また、急なご相談も対応可能です。まずはお問い合わせください。
費用について
標準負担額とは、月2回の訪問および24 時間診療体制のために要する1ヶ月あたりの負担金額の目安です。
| 対象 | 負担割合 | 標準負担額 | |
|---|---|---|---|
| 居宅 | 高齢者 | 1割 | 約6,000円 (月1回の場合約3,000円) |
| 3割 | 約18,000円 | ||
| 一般 (70歳未満) |
3割 | 約18,000円 |
- 介護保険利用者の方は、居宅療養管理指導料(1割:588円、2割:1,176円、3割:1,764円)が必要です。
- 各種検査を行った場合、在宅酸素や胃ろう、気管切開などの医療処置がある場合、臨時往診があった場合は、別途費用が加算されます。
- ご自宅にて処方箋を発行しますが、薬剤費は別途必要です。
※上記は居宅訪問時の診療費用の概算を示しております。施設への訪問は担当患者数によって異なるため、別途お問い合わせください。
ききょう会の在宅ホスピスケア
ききょう会は一般的な訪問診療はもちろん行っておりますが、とくに在宅ホスピスケア・在宅緩和ケアに強みを持っています。 在宅ホスピスケアや在宅緩和ケアについては詳しくはこちらをご覧ください。
「自分らしくご自宅で人生の最期を迎える」
患者さんが望む最期を迎えられるよう、ききょう会は高度な医療やチーム連携を行うことで在宅ホスピスケア・在宅緩和ケアを提供しています。
そのために、ききょう会では研修の実施、マニュアルの作成、患者さん用の分かりやすい資料作成、ICTツールの活用等を積極的に行うことで医療の品質向上への取り組みを行っております。
研修・マニュアルによる品質向上と均質化
ききょう会では複数のクリニックを運営しており、複数のクリニックの事例を共有する研修を定期的に行うことでスキルアップを図っています。 また、これまでに培われた経験を蓄積し、ききょう会独自のマニュアルを作成しています。
このマニュアルは、提供する医療品質の担保と患者さんの安心安全を向上させるのに役立っています。
在宅ホスピスケア・在宅緩和ケア マニュアル
患者さんや関係者のための分かりやすい資料
最期の時間というのは患者さんにとっては初めて経験するものです。家族にとっても初めてということがほとんどです。
そして、患者さんや家族の一番の不安は、急に分からないことが起こることです。
当院ではすべての職種がこれを共通認識として持っております。
そのため、ききょう会では最期を迎えるにあたっての分かりやすい資料を提供しています。
資料に目を通すことによって、今後の過ごし方について身体の変化やケアの仕方が分かり、家族で話し合うための時間や、心に落ち着きやゆとりを持つことをサポートします。
特に、下記『これからの過ごし方について』のご案内は、しかるべきタイミングでお渡しさせていただくのですが、「実際にその通りになったのでびっくりしました」「これがあったので慌てなくてすみました」という声をよくいただきます。
ICTの積極利用
利用しているICTツールの一例ですが、当法人では医療介護チーム連携用のコミュニケーションツールを使用しています。
在宅ホスピスケア・緩和ケアにおいては、クリニックの医師、看護師、相談員だけではなく、訪問看護ステーションの看護師、薬局の薬剤師、訪問介護の介護士、居宅介護支援事業所のケアマネージャーなど、多事業所、多職種の連携が不可欠です。
そのため連携がスムーズにいかないと、提供するサービスの質が向上しません。
当法人ではメディカルケアステーションという医療介護チーム連携用のコミュニケーションツールを使用し、他の事業所にも使用してもらうことで情報連携をスムーズにしています。
患者さんの状態を確認して医師が訪問看護ステーションの看護師に指示を出したり、その指示をケアマネージャーが確認しケアプランの作成に活かしたり、家族が見れるようにしておけば状況がリアルタイムで分かるので家族も安心です。
ききょう会の在宅ホスピスケアについて職員インタビュー
在宅ホスピスケアは最期を迎えるにあたって患者さんや家族のQOLを最大化させることにありますが、その方法は患者さんによって十人十色で一義的に決まることではないと思っています。
ききょう会が大事にしている在宅ホスピスケアの考え方についてスタッフインタビューを行っておりますので、考え方の参考にしていただけたらと思います。